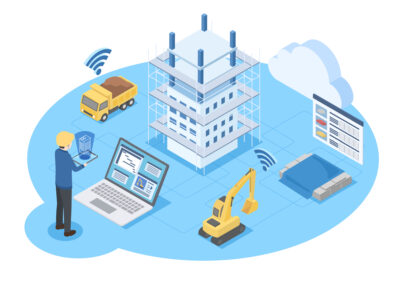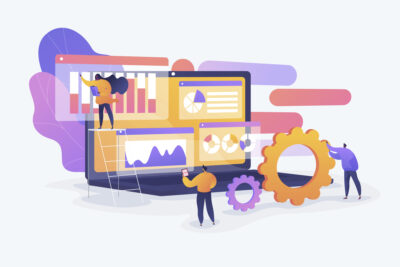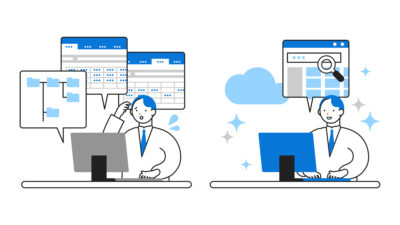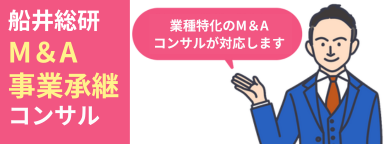いつもお世話になっております。船井総合研究所の高階でございます。
今回のコラムでは、多くの企業が取り組む「改革」や「DX」について、単なるコストカットで終わらせず、企業の未来を創る「営業実績の向上」と「人材の成長」に繋げるための本質的なアプローチをご紹介したいと思います。
コスト削減の先に目指す持続的成長のために
「会社の改革」や「DX 推進」と聞くと、多くのビジネスパーソンがまず「経費削減」や「業務効率化によるコストカット」を思い浮かべるのではないでしょうか。
もちろん、それらも重要な成果の一つです。しかし、守りの改革だけでは、企業の未来を切り拓く力は生まれません。
よく言われているのは、取り組みで削減できた時間をより付加価値高い活動に費やそう、という話です。
この“付加価値高い活動”というのは抽象度も高く便利な言葉ではありますが、つまるところ何なのかというのをよく考える必要があります。
私は、“付加価値高い活動”というのは、自社で働く「人」が成長し、その結果として「収益」という形で事業が成長する、攻めの姿勢を生むことなのではないか、と考えています。
今回は、コスト削減という目先の効果に留まらず、営業チームを強くし、一人ひとりの成長を促し、持続的な事業成長を実現するために「本当にやるべきこと」は何か、その核心に迫りたいと思います。
成長企業で起きていること
事業が順調に成長し、組織が拡大していくフェーズは、喜ばしい反面、多くの企業が「成長の壁」に直面する時期でもあります。かつての少数精鋭時代には問題にならなかったことが、組織の至る所で静かに、しかし確実に問題を引き起こし始めます。
・疲弊する営業現場と「見えないコスト」の増大
売上目標は右肩上がりに伸びていく一方で、営業の「やり方」は昔のまま。結果として、個々の営業担当者への負担が雪だるま式に増えていきます。顧客と向き合う時間よりも、社内向けの報告書作成や会議のための資料準備に追われ、本来最も価値を生むべき活動が圧迫されていくのです。
この「見えないコスト」は、残業時間の増加やエンゲージメントの低下に繋がり、最悪の場合、将来を期待された優秀な人材の離職という、企業にとって最も手痛い損失を引き起こす原因ともなり得ます。
・機能不全に陥る営業マネジメント
メンバーが増えるにつれ、マネージャーはプレイング業務とマネジメント業務の板挟みになります。私もマネジメント経験者ですが、部下一人ひとりの活動状況を詳細に把握することは困難になり、指導やアドバイスは、どうしても自身の「勘」や「経験」に頼らざるを得なくなった経験があります。
部下の活動がブラックボックス化することで、案件がなぜ失注したのか、誰が何に困っているのかを正確に把握できず、適切なタイミングでのフォローができません。
果たして自分のアドバイスはピントが合っているのか。それすらも分からない苦しい時間を過ごすことになります。
これでは、チーム全体のパフォーマンスを底上げすることは難しく、マネージャー自身も成果を出せない焦りから疲弊していくという悪循環に陥ります。
・属人化し、失われていく「勝つためのノウハウ」
どんな組織にも、突出した成果を上げるエース級の人材が存在します。しかし、その成功の秘訣が言語化・共有化されず、個人の「暗黙知」のままであれば、それは組織の資産にはなり得ません。
新入社員や若手は、その背中を見て学ぶしかなく、成長には非常に時間がかかります。
さらに深刻なのは、ベテラン社員やエースの退職です。彼らが去ると同時に、長年かけて培われた貴重な営業ノウハウや、顧客との深い関係性といった無形資産がごっそりと失われてしまうのです。
統合情報管理の重要性
前章で挙げた課題の根底に共通して横たわっている問題、それは「情報の分断」です。
顧客情報、担当者情報、商談履歴、成功事例、クレーム情報といった、企業の生命線ともいえる情報が、個人の PC や手帳、メールボックス、そして頭の中に散在している状態。この「サイロ化」こそが、組織の成長を阻害する最大の要因と言えます。この問題を解決する鍵が「統合情報管理」です。
これは、単にデータを一箇所に集めることではありません。バラバラに存在していた情報を有機的に繋ぎ、組織全体で活用できる「知のプラットフォーム」を構築することを意味します。
統合情報管理が実現すると、企業には 3 つの大きな変化がもたらされると考えています。
第一に、「顧客理解の劇的な深化」が挙げられます。
マーケティング部門がいつ顧客と接点を持ち、営業担当者が過去にどんな提案をし、カスタマーサポートがどのような問い合わせに対応したのか。
こういった情報が統合されることで、初めて顧客を 360 度、立体的に理解することができます。
この深い理解こそが、顧客の心に響く最適なアプローチを可能にし、長期的な信頼関係(LTV の向上)の礎となるわけです。
第二に、「データドリブンな文化の醸成」です。
情報が整備され、誰もが必要なデータにアクセスできる環境は、データに基づいた客観的な意思決定を促します。
例えば、失注案件のデータを分析すれば、価格が問題だったのか、機能が足りなかったのか、あるいは提案のタイミングが悪かったのか、といった敗因を特定し、次の戦略に活かすことができます。
勘や経験に頼るギャンブル的な営業管理ではなく、データという事実に基づいた科学的な営業管理へと進化できるのです。
そして最後に、「組織学習能力の向上」です。
成功した提案書や、顧客に響いたトークスクリプトが共有されれば、それはチーム全体の教科書となりえます。
この活動を通して、組織全体で学習・成長していくサイクルが生まれていきます。データをまとめること自体に意味はなく、それを活用することにこそ価値があるのです。
営業部門が取り組むべきデジタル化とは
前述した「統合情報管理」を実現するための具体的な手段として紹介したいのが、「営業部門のデジタル化」です。
しかし、ここで注意すべきは、高価なシステム(SFA や CRM など)を導入すれば全てが解決するわけではない、ということです。SFA や CRM は導入すればすぐ売り上げが 2 倍になる、というような魔法のツールではありません。
重要なのは、ツールを導入すること自体ではなく、それを使って「業務を変革し、人の成長を促す」という明確な目的意識です。
営業部門が取り組むべきデジタル化には、3 つの段階があると考えています。
■ステップ 1:顧客接点情報の資産化(データ化)
まずは、日々の営業活動の記録を「未来のための投資」と位置づける意識改革が必要です。
日報や週報は、上司に報告するためだけの義務作業ではありません。入力された一件一件の活動履歴が、未来の営業戦略を立てるための貴重なデータ資産となるのです。
ただし、注意していただきたいポイントとして、スマートフォンなどからでも簡単に入力できる仕組みを整えるなど、営業担当者の負担を限りなくゼロに近づける工夫が不可欠です。
■ステップ 2:ナレッジ共有の仕組み化
次に、個人が持つノウハウを組織の力に変える仕組みを構築しましょう。
例えば、大型案件を受注した際の提案書や、難易度の高い質問への切り返しトーク、序盤のヒアリング項目などを、誰もが簡単に検索・閲覧できるプラットフォームを用意しましょう。
これにより、新人はトップセールスの知恵を借りながら成長できますし、チーム全体で成功パターンを再現できるようになります。
これは、形骸化しがちな OJT を補完し、人材育成のスピードを飛躍的に高めることに繋がります。
■ステップ 3:情報連携のシームレス化
最終的には、マーケティングから営業、そしてカスタマーサポートまで、顧客に関わる全部門の情報をデジタルプラットフォーム上で連携させます。
Web サイトから問い合わせをしてくださった見込み顧客の情報が、即座に担当営業に通知される。さらに、過去の閲覧履歴や興味関心を踏まえた上で、個別に最適化したアプローチを開始する。このように、部門の壁を越えて一貫した“質の高い”顧客体験を提供することで、対応のスピードと質が向上し、顧客満足度は大きく高まっていきます。
攻めの発想でDXを推進する
本稿でお伝えしたかったのは、真の DX は「経費削減」といった守りの発想だけではなく、
「どうすればもっと売上を伸ばせるか」「どうすれば社員がもっと成長できるか」という攻めの発想が非常に重要である、ということです。
情報の分断が組織の成長を阻害し、情報の統合が組織を強くする。このシンプルな原則を理解し、デジタル技術を賢く活用して「情報を組織の力に変える」こと。それこそが、これからの時代に持続的な成長を遂げる企業が行うべき、本質的な改革といえるでしょう。
セミナー開催のご案内
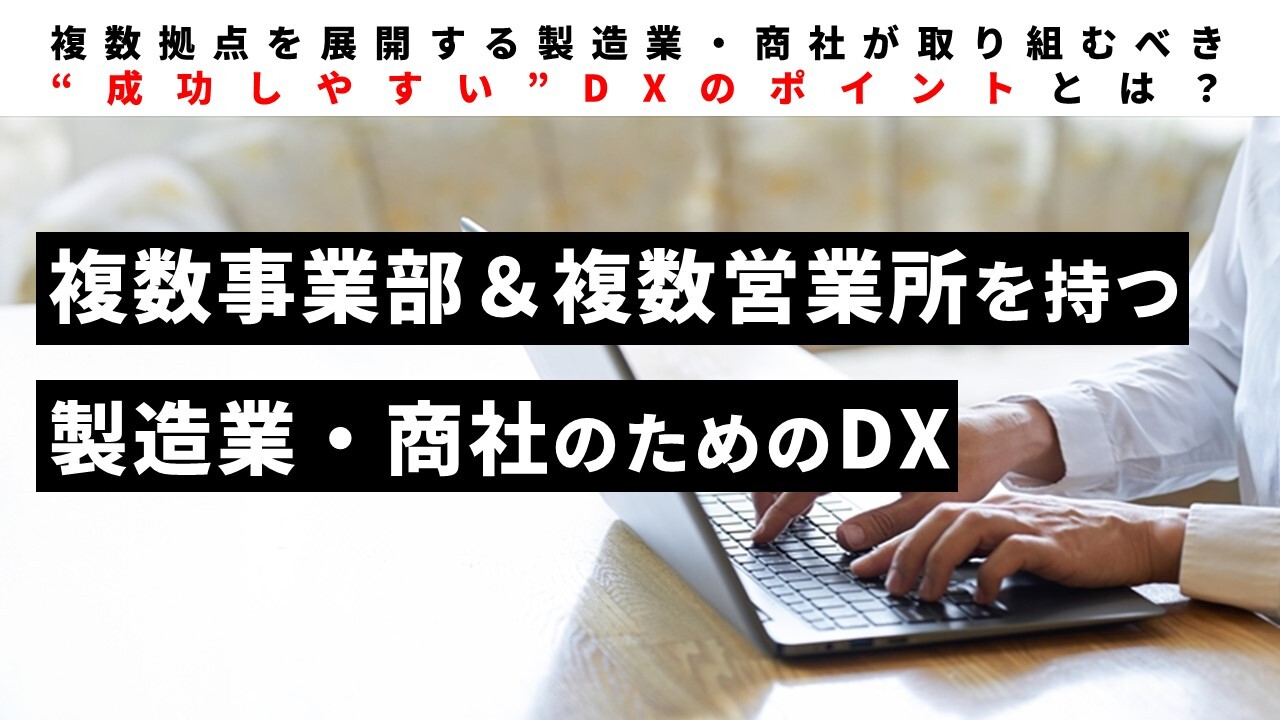
https://www.funaisoken.co.jp/seminar/129678
このような方におススメのセミナーです。
「複数事業部、複数営業拠点が存在し、営業マネジメントが上手くできていない」
「営業会議のために複数のシステムからデータを集めてなければならず、工数がかかっている」
「営業活動の多くが属人化していてアナログに依存している」
という方向けに
「複数事業部&複数営業所を持つ製造業・商社のためのDX」を開催いたします。
ぜひ、経営者の皆様と、貴社システムご担当の皆様と、
ご一緒に本セミナーへのご参加を検討いただければと思います。
皆様のご参加を心よりお待ちしております。
【セミナー概要】
日程◆2025年➀7月11日 (金)、②7月15日(火)、③7月17日(木)
※上記日程からご都合のよい日程をお申込みください。
開催形式◆Webセミナー
時間◆13:00~15:00