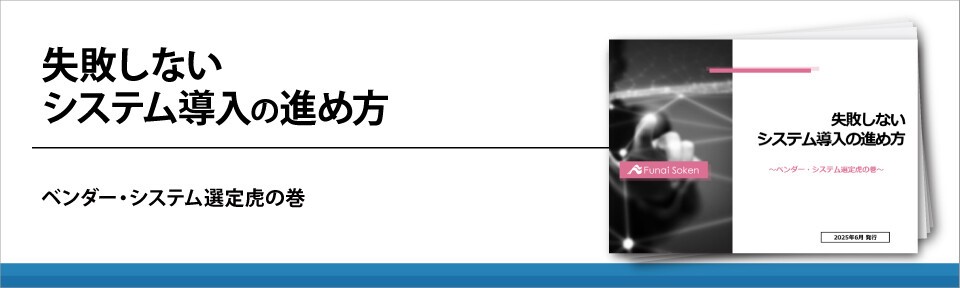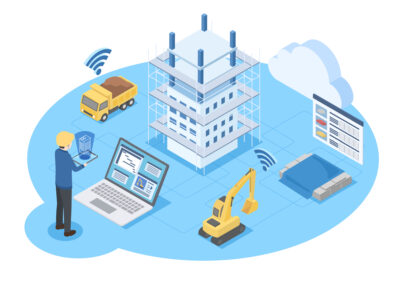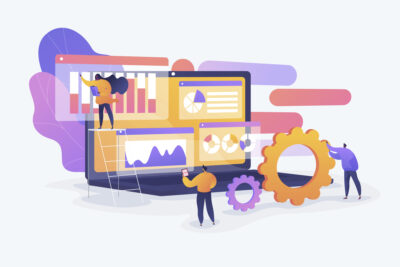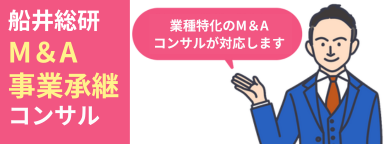失敗しないシステム導入のために理解すべきベンダー選定の重要性
システム開発やシステムの運用保守を外部の企業に依頼する場合、その依頼先であるベンダーを選定するプロセスは、プロジェクト全体の成功を決定づける非常に重要な要素となります。IT業界においては、システム構築を行った後にDX(デジタルトランスフォーメーション)へと繋げる動きが増加しており、ベンダー選定は単なるコスト削減や短期的な課題解決に留まらず、自社のIT戦略や将来的なビジネスパートナーシップを決定する上で極めて重要な意味を持ちます。
しかし、システム導入プロジェクトの約70%が期待した成果を出せていないというデータもあるほど大きな課題感が存在します。その主な原因としては、計画段階での考慮不足、現場ニーズの把握不足、スコープの曖昧さ、要件定義の不明確さによる仕様変更の多発、そしてベンダーとのコミュニケーション不足や「丸投げ」によるプロジェクト管理不足などが挙げられます。特にベンダー選定においては、「とりあえずDX」といったトップダウンの指示と現場ニーズの乖離、またはコスト重視のみの選定により、品質や保守に問題が生じるケースが少なくありません。
このような失敗を避けるためには、その時の印象や直感、価格の安さだけで安易にベンダーを選択するのではなく、自社に合った最適なベンダーを明確な基準で選定することが不可欠です。私たちは、システム導入はあくまで「手段」であり、その真の目的は「業務改革」と「経営課題の解決」にあると認識しております。適切なベンダー選定を通じて、この目的を達成するための基盤を築くことが何よりも大切になります。
成功を導くシステム選定のポイント~事前調査と準備~
ベンダー選定を成功させるためには、体系的かつ段階的なプロセスを踏むことが不可欠です。
一般的に、ベンダー選定は以下の三つのフェーズに沿って進められます。
1. 事前調査フェーズ
このフェーズでは、システム導入の可能性を秘めたベンダーの情報を幅広く収集し、候補を絞り込みます。 まずは、ベンダー候補調査を行います。候補は何社でも構いませんが、後の選定作業の労力を考慮すると、この段階で10社程度に絞り込めるのが理想的です。情報収集は、企業のウェブサイトや実績紹介、簡単な問い合わせを通じて行うのが一般的です。大手企業は信頼性が高い一方でコストも高くなりがちなため、中小企業やベンチャー企業も含めて幅広く検討することが有効です。
次に、RFI(情報提供依頼書)の作成・送付を行います。RFIはベンダーに対して基本情報、製品情報、技術情報などの資料提供を依頼するものです。ベンダーごとに提供してもらう情報が異なると比較が困難になるため、RFIには送付した趣旨や目的を明確にし、企業から必要な情報を正確に提供してもらえるような統一フォーマットを作成することが重要です。回答納期は通常1〜2週間程度を目安とします。
2. 選定準備フェーズ
事前調査の結果に基づき、具体的な提案を募るための準備を進めるフェーズです。 RFIの回答が届いたら、まずはその内容を確認し、自社の趣旨や目的に合わないベンダーを除外します。この段階でベンダー候補を5〜6社程度に絞り込むことが望ましいです。 その後、残ったベンダー候補に対してRFP(提案依頼書)の作成・提出を行います。RFPは、自社の概要、システム導入の目的、現状の課題、具体的な要望などを詳細に記載し、ベンダーに提案書を依頼する文書です。これにより、ベンダーは自社の実情に合った最適な提案を作成しやすくなり、ユーザー企業とベンダー双方の認識を合わせる重要な役割を果たします。RFPには、提案を依頼したい範囲、機能要件・非機能要件、テスト・移行・教育要件、プロジェクト体制などを具体的に含めると良いでしょう。
RFPの作成と同じタイミングで、提案内容を比較検討するための評価項目を作成することが重要です。これが「明確なベンダー選定基準」にあたり、特定のベンダーへの肩入れを防ぎ、客観的な比較を可能にします。可能であれば、RFP作成時点で評価項目を策定し、RFPにあらかじめ明記することで、ベンダーからより自社の希望にマッチした提案を引き出すことができます。
3. 評価・選定フェーズ
ベンダーからRFPに対する提案書が返却されたら、まずはその内容を隈なく確認します。不明点や疑問点があれば、ベンダーに問い合わせて解消しておくことが重要です。場合によっては、ベンダー側のPM(プロジェクトマネージャー)候補にプレゼンテーションを実施してもらい、その力量や人となりを見極めることも有効です。直接の質疑応答は、ユーザー企業とベンダー双方の認識のずれをなくす絶好の機会となります。
全てのベンダーの情報が集まったら、事前に作成した評価項目に沿ってベンダーを評価します。この際、抽象的な評価ではなく、各項目を具体的に採点し、数値化することが大切です。最終的に数社程度まで候補を絞り込んだ後、数値に表れないプロジェクトへの意欲やコミュニケーションの取りやすさなども含めて、プロジェクトメンバー間で徹底的に議論を重ねます。必要に応じて追加情報を収集し、自社にとって最も最適なパートナーとなる1社を決定します。
ベンダー選定基準を設定する際には、多角的な視点から評価を行う必要があります。
ここでは、まずベンダー「会社」の観点から重要なポイントを二つご紹介します。
•事業継続性、安定性
ベンダーの事業継続性と安定性は、長期的な関係性を求める場合に特に重要になります。万が一、プロジェクト進行中にベンダーが倒産したり、事業を縮小したりするリスクがある場合、プロジェクトが頓挫したり、システム稼働後の運用・保守体制が不安定になったりする可能性があります。そのため、ベンダー選定の際には、まず事業継続性と安定性を必ず選定基準に含めるようにしましょう。
•過去実績、能力
ベンダーの能力を確認するためには、過去の実績を参照することが有効です。自社が開発を依頼したいシステムと類似した案件の経験があるか、同じ技術を用いた案件を担当したことがあるかなどを確認します。ベンダーのウェブサイトで情報が不十分と感じる場合は、RFIを活用して過去実績の提供を依頼し、きちんと評価できる体制を整えるべきです。また、コンサルタントとしては、担当するSE体制の資質・能力も総合的に評価することが肝要であると考えています。
システム提案内容を評価する重要ポイント費用と機能とは
ベンダー選定において、会社自体の信頼性だけでなく、具体的な「提案内容」を精査することも極めて重要です。
ここでは、提案内容の観点から特に重要な評価ポイントを掘り下げて解説します。
• 要件の網羅性、実現度
RFPに記載した自社の要件や課題、目的が、ベンダーの提案によってどこまで網羅され、実現可能であるかを細かく確認する必要があります。すべての要件が満たされていることが理想ですが、技術的制約や予算の都合で実現できない要件がある場合は、ベンダーが適切な代替案を提示できるか、またその要件が実現できないことによる影響を事前に調査し評価することが大切です。この段階で実現可能性を正確に把握していないと、プロジェクトが途中で中断するリスクが高まります。
• イニシャルコスト、ランニングコスト
システム導入にかかる初期費用(イニシャルコスト)と、導入後の運用・保守にかかる費用(ランニングコスト)は、自社の予算内に収まるか、見積もり額が妥当であるかを慎重に吟味する必要があります。コストの安さだけで選定すると、品質の低いシステムが導入され、結果的に高コストになる可能性も考えられます。特に大規模なプロジェクトでは追加要件が発生しがちですので、余裕をもったコスト計画を評価基準に含めることが賢明です。
• スケジュールの妥当性
提案されたスケジュールが、自社のビジネスチャンスを逃さない現実的なものであるか、またベンダーが無理なスケジュールで開発を行おうとしていないかを確認することが重要です。納期が遅すぎると機会損失に繋がり、逆に早すぎると品質低下のリスクがあります。自社とベンダー双方のリソースを考慮した、合理的なスケジュールであるかを見極める必要があります。
• 開発体制と妥当性
ベンダーの開発能力を超えた体制になっていないか、想定される作業量と人員数が適切かを確認することは非常に重要です。プロジェクトマネージャー(PM)の経歴や能力、チーム内外とのコミュニケーション方法、そして下請け企業を含めた全体的な体制なども評価の対象となります。
• 保守体制と妥当性
システムリリース後の保守体制は、長期的な運用を見据える上で欠かせません。ベンダーが契約獲得のために保守運用コストを低く見積もって提案してくる可能性もあるため、システムリリース後の想定される作業内容とベンダーの想定コストが妥当であるかを正しく評価することが必要です。サポート内容、期間、費用、障害発生時の対応フローなどを詳細に確認しましょう。
• アプローチやプロジェクトに対する考え方
今回のプロジェクトの位置づけをベンダーが正しく認識しているかを確認することも、評価基準としては重要です。例えば、DX推進を目的としている場合、ベンダーがその方向性を理解し、協力する姿勢があるかどうかは、プロジェクトの成功に大きく影響します。
• プレゼンテーション
ベンダーのプレゼンテーションは、プロジェクトに対する意気込みやコミュニケーション能力を表す重要な機会です。資料の見やすさ、説明の簡潔さ、質疑応答のスムーズさなどを評価項目に盛り込み、特にPMの人となりや経験の豊富さなど、書類だけでは分からない人間性を実際に対面して見極めることが大切です。
その他として、契約形態(委任契約か請負契約か)や、開発した設計書などの資産の帰属先といった点も、選定基準に含めるべき重要なポイントになります。
失敗しないための客観的な数値化と総合的判断による選定評価法
ベンダー選定を成功させるためには、感覚的な判断ではなく、明確な根拠に基づいた客観的な評価が重要です。
具体的な評価方法の流れと、選定時の注意点について解説します。
評価方法の流れ
➀評価ポイントを決める
ベンダーからの提案内容やプレゼンテーションを評価するための切り口を定めます。
主に「ベンダーの信頼性」「要件に対する適合性」「プロジェクト体制の妥当性」の三つに分類できます。
②評価項目を決める
評価ポイントの内訳となる具体的な評価項目を設定します。例えば、ベンダーの事業継続性・安定性、開発実績・得意な分野、コスト、要件の網羅性・実現度、開発・保守体制、セキュリティ体制、プレゼンテーションの評価などが挙げられます。
➂評価項目の配点を決める
各評価項目を数値化し、定量的に表現するために配点を振り分けます。シンプルに「○△×」の3段階評価で点数を設定したり、自社が特に重視する評価項目に重み付けをしたりすることで、より自社の優先順位を反映した評価基準を作成できます。各項目の合計が100点になるように調整すると、集計や比較が容易になります。
➃評価結果を比較する
全てのベンダー候補で評価が集計できたら、結果を比較します。総合点が高いベンダーが最有力候補となりますが、プレゼンテーション時の雰囲気やプロジェクトに対する意欲など、数値には反映されない評価ポイントも含まれる場合があります。プロジェクトメンバー間で協議を重ね、必要に応じて点数調整も行いながら、自社にとって最も相応しいベンダーを選定することが重要です。
まとめ
システム導入は、単なるツールの導入ではなく、「業務改革」と「経営課題の解決」を目的とした重要なプロジェクトです。テクノロジーそのものよりも、それを使う人と組織の変革にこそ成功の鍵があります。
本コラムが皆様の効率的で確実なシステム選定の一助となりましたら幸いです。
船井総合研究所では、システム導入前の企画・要件定義から、ベンダー選定、導入後の定着化まで、一気通貫でサポートしております。ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
以下にシステム選定、ベンダー選定の最新レポートをご紹介しています。ご興味があれば是非ダウンロードいただければと思います。