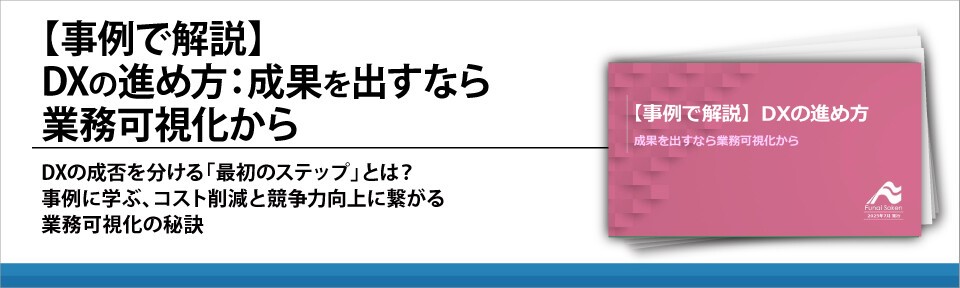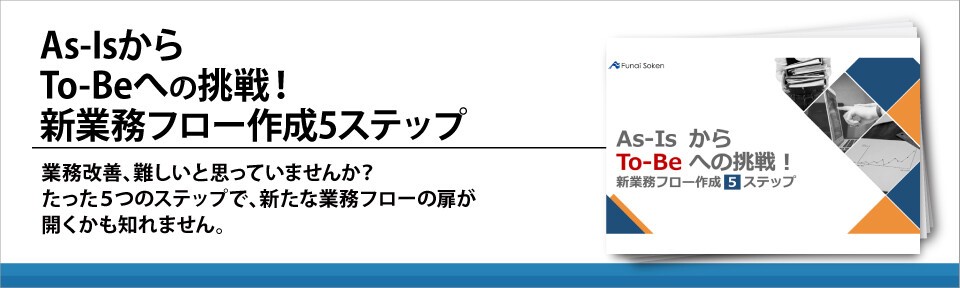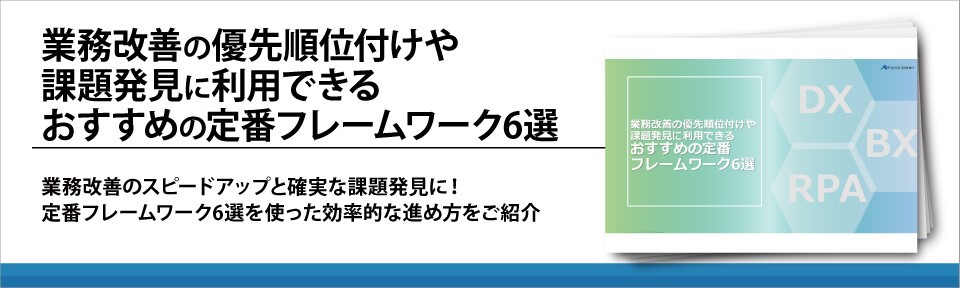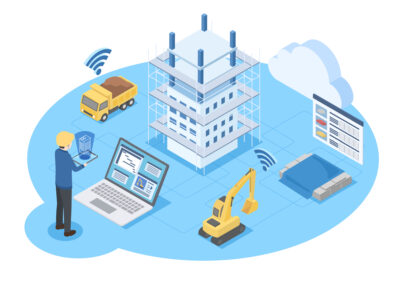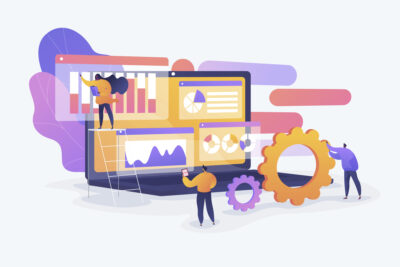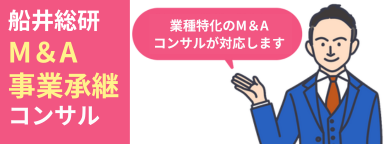業務改善とは、現状の業務に存在する「ムリ・ムダ・ムラ」をなくし、より良い業務プロセスを設計するための一連の取り組みです。
単なる業務効率化に留まらず、企業の生産性向上やコスト削減、従業員のモチベーション向上、さらには顧客満足度の向上といった多岐にわたるメリットをもたらします。特に、労働人口の減少や働き方の多様化が進む現代において、限られたリソースで成果を最大化するためには、業務改善が不可欠です。
この業務改善を成功に導く上で重要なのが、「課題分析」です。
ここでいう「課題分析」とは、真の要因を特定し、そのギャップを埋めるための具体的なアクションを策定することを意味します。
課題分析を疎かにし、表面的な問題にのみ対処すると、費用対効果の低い改善に終わるか、あるいは新たな非効率を生み出してしまうリスクがあります。
本コラムでは、業務改善における課題分析のポイントについて、わかりやすく解説いたします。
「ムリ・ムダ・ムラ」を特定するための見える化
業務改善を効果的に進めるためには、まず現状の業務プロセスを正確に把握し、課題を「見える化」することが必要です。
現行業務を可視化することで、業務に潜む「ムリ・ムダ・ムラ」といった非効率な点やボトルネックを特定しやすくなり、課題に対する組織内の共通認識を持たせることにつながり、効果的な改善策を検討するための基礎を築くことができます。また、正確な情報共有が可能となることで、コミュニケーションの円滑化や認識齟齬の抑制にもつながります。
特にパソコンで主たる業務を実施する場合には、視覚的にも物理的にも業務内容がブラックボックス化になる傾向が強いため、「業務の見える化」を徹底することで、表面的な問題だけでなくその根本原因を特定し、より質の高い改善活動へと繋げることが可能になります。
業務可視化の際には、「何を」・「どれくらい」・「どのように」の3つの観点で情報を整理することが有効です。詳細は下記の無料冊子にて別途解説しておりますので併せてご覧ください。
根本原因を特定する課題分析の手法とフレームワーク
業務内容から課題の「見える化」に成功したら、次にその根本原因を特定するステップへ進みます。
根本原因を深掘りするために、以下のフレームワークが役立ちます。
①:なぜなぜ分析
一つの問題に対し「なぜ?」を5回程度 繰り返し問いかけることで、表面的な原因の奥にある真の原因を突き止める手法です。
その際に気を付けるべきは、特定の個人を問題の原因としないことです。もし「なぜ?」の行きつく先が「○○さんが不注意だから」であればその方への注意で終わってしまいますが、仕組みや体制に目を向けることで根本的な解決に向けた生産的な議論につながります。
②:ロジックツリー
問題点を樹木のように枝分かれさせ、論理的に原因や解決策を探るフレームワークです。
大きな問題から小さな要素へと分解し、階層化することで、複雑に絡み合った課題の構造を整理し、注力すべきポイントやボトルネックを特定できます。
③As-Is / To-Be
現状(As is)と理想の姿(To be)を明確に記述し、その間のギャップを分析するフレームワークです。
現状と理想の状態を具体的に描くことで、なぜその理想に到達できないのか、その障壁となっている根本的な原因を洗い出すことができます。
現状の業務フローの可視化とあるべき業務フローの設計については、下記の無料冊子にて詳しく解説しておりますので併せてご覧ください。
上記のようなフレームワークで情報を整理する際には、「MECE」を意識すると効果的に進めることができます。
「MECE(Mutually Exclusive and Collectively Exhaustive)」とは「漏れなく、ダブりなく」のように訳される語で、課題の全体像を正確に捉え、原因の特定や解決策の検討を論理的に進めることを可能にするフレームワークです。
例えば、「残業時間が多い」という事象の原因をロジックツリーで分析する際、モレなくダブりのない大きな要素に分解すると、「業務量が多い」と「生産性が低い」の2つに集約されます。この2つは互いに重複せず、これ以外の大きな原因は考えにくいため、MECEな状態と言えます。その後も、同様の要領で上記の2点の原因をMECEに整理してゆくと、真因を特定することができます。
これらのフレームワークを活用することで、主観や思い込みに左右されず、客観的な視点で課題を深掘りし、その真の要因を特定することが可能になります。これにより、対症療法ではなく、持続的な改善に繋がる本質的な解決策を導き出すことができるでしょう。
今回ご紹介したような、業務改善における課題発見や優先順位付けに利用できるフレームワークを、下記の無料小冊子にて図解付きでわかりやすく説明しています。ぜひお手元に置いてご活用ください。