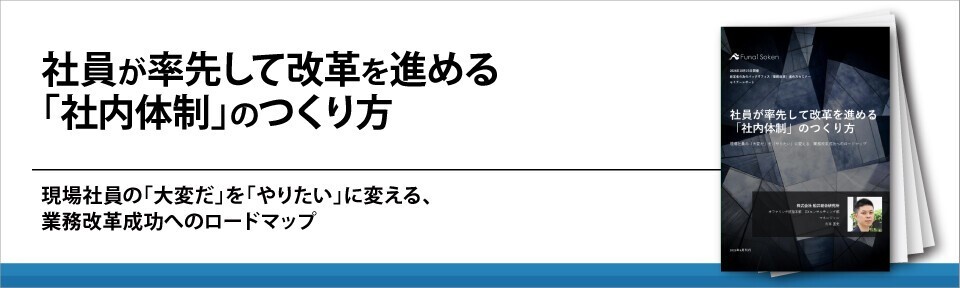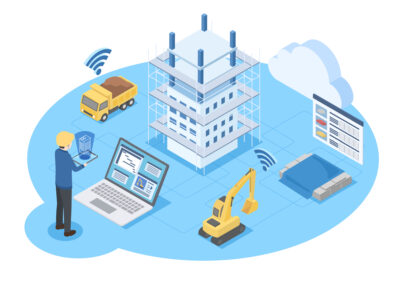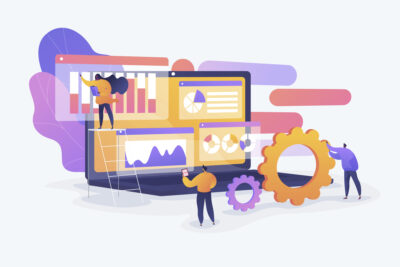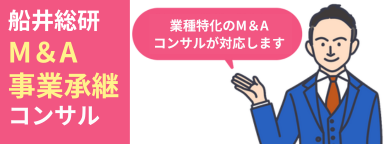なぜシステム導入は業務改革に繋がらないのか
「最新の高価なシステムを導入したのに、現場の業務が楽にならない」「多額の投資をしたが、効果が見えない」——。
多くの企業で、このような悩みが聞かれます。DX(デジタルトランスフォーメーション)戦略の柱としてシステム導入を進めたにもかかわらず、期待した成果が得られないという現実は、決して珍しいものではありません。この問題の根源は、いつの間にかシステムの導入そのものが目的化してしまい、その価値を最大限に引き出すために不可欠なBPR(ビジネスプロセス・リエンジニアリング)、すなわち「業務改革」の視点が欠落している点にあります。
近年、この課題への解決策として、システムの標準機能に業務を合わせる「Fit to Standard」というアプローチが提唱されています。しかし、本稿ではその思想をさらに一歩進め、理想論に終わらせないためのより実践的な業務改革手法として、「Fit & Gap & Restructure」という新たなフレームワークについて論じます。
「Fit to Standard」の理想と、現場で生じる誤解
システム導入プロジェクトにおけるパラダイムシフトとして「Fit to Standard」が提唱されるようになった背景には、明確な戦略的価値が存在します。これは、コストを抑え、短期間での導入を可能にするだけでなく、業務プロセスの標準化と効率化を促し、組織全体の生産性を向上させる極めて強力な起爆剤となり得るからです。
「業務ノウハウの集合体」としてのシステム
「Fit to Standard」とは、システムの標準機能を「あるべき姿(To-Be)」と捉え、自社の業務プロセスの方をシステムに合わせて変革していくという、従来とは真逆の発想です。現代の優れたパッケージシステム(ERPやSaaS)は、単なるツールではありません。それらは世界中の企業の成功事例や業界のベストプラクティスが凝縮された「業務ノウハウの集合体」なのです。自社の旧弊なプロセスを維持するためにカスタマイズを重ねることは、この業界全体の知見を意図的に放棄する行為に他なりません。
現場で生じる誤解と抵抗
しかし、このアプローチは現場で「単にシステムに業務を合わせるだけの思考停止」と誤解されるリスクを孕んでいます。業務改革は必ず痛みを伴うため、「これは長年のやり方だから」「わが社は業務が特殊だから」といった声が必ず上がります。これらの声は、現状の業務プロセスを客観的な見直しの対象外とする「聖域化」を招き、改革の実行を著しく困難にします。リーダーが乗り越えるべき最初の、そして最大の壁は、この組織の慣性なのです。
このように、「Fit to Standard」の思想をスローガンで終わらせず、実践的な行動に落とし込むための、より具体的なフレームワークが必要となります。
発想の転換:「Fit & Gap」を「改革の種」として再定義する
旧来のシステム導入において「Fit & Gap」分析は、改革の足かせとなることが少なくありませんでした。
DX戦略を通じた業務改革を駆動するためには、まずこの分析の役割そのものを根本から再定義することが不可欠です。
■カスタマイズを目的とした旧来の「Fit & Gap」
従来の「Fit & Gap」分析は、自社の既存業務プロセス(As-Is)と導入システムの機能との差分(Gap)を特定し、
そのGapを追加開発(カスタマイズ)で埋めることを目的としていました。しかし、このアプローチは多くの弊害を生み出します。
- ・コストと期間の増大:カスタマイズがプロジェクトの予算とスケジュールを大幅に圧迫する。
- ・システムの複雑化:独自の改修がシステムを複雑にし、特定の担当者しか理解できない状況を生み出す。
- ・変化に対応できない「塩漬け」システム:過度なカスタマイズの結果、将来のアップデートが困難になり、システムが陳腐化。変化の速い時代に対応できず、企業の足かせとなる。
■「改革の種」を発見するための新しい「Fit & Gap」
本稿の核心は、新しいアプローチにおける「Fit & Gap」分析の目的が180度異なるという点です。発見された「Gap」は、もはや追加開発で埋めるべき「問題点」ではありません。それは、自社の非効率なプロセスや聖域化された慣習を客観的に炙り出し、変革を促すための貴重な「改革の種」として捉え直されるのです。この発想の転換こそが、システム導入を業務改革へと繋げるための第一歩となります。しかし、「改革の種」を見つけただけでは意味がありません。重要なのは、その種をいかにして芽吹かせ、具体的な改革の果実として実らせるか、すなわち次の再構築のプロセスです。
「Restructure」の実践:システムを「触媒」として業務を再構築する
「Fit & Gap」分析によって発見された「改革の種」を、具体的な業務改革、すなわち「Restructure」に繋げるプロセスこそ、DX成功の核心です。システムは答えそのものではなく、この変革を加速させるための強力な「触媒」として機能します。
■ゼロベースで描く業務プロセスの再構築
「Restructure」は、以下の3つの要素を軸に実行されます。
- 1.ゼロベースでの業務プロセス再構築 改革の核心は、既存業務の延長線上で物事を考えないことです。「これまでこうだったから」という言葉を禁句とし、システムの標準機能が示すベストプラクティスを羅針盤としながら、ゼロから理想の業務フローを描き出すことが求められます。
- 2.何かを「捨てる」勇気 この改革プロセスで最も問われるのは、何かを「追加」することではなく、長年の慣習により続けられてきた非効率な業務の中から、何を「捨てる」かを決断する勇気と覚悟です。この痛みを伴う意思決定こそが、筋肉質な業務体質への転換には不可欠です。
- 3.システムを強力な「触媒」とする システムは、導入するだけで魔法のように問題を解決してくれる「答え」ではありません。その本質的な役割は、自社の古いやり方や非効率なプロセスを変えるための強力な「触媒」となることです。システムの標準機能とのGapを起点に、「なぜ、そのやり方なのか?」という問いを組織に投げかけ、変革を促します。
■改革を断行する二つの要諦
この困難な改革を断行するには、2つの要素が極めて重要になります。一つは「経営層の強いコミットメント」です。トップが改革のビジョンを明確に示し、自ら障害を排除する覚悟を表明しなければ、いかなる改革も組織の慣性に飲み込まれます。
もう一つは、現場の理解と協力を得るための「丁寧なコミュニケーション」です。一方的な指示ではなく、なぜ業務フローの変更が必要で、それによってどんなメリットが生まれるのか(例:「面倒な手作業がなくなる」「判断に必要な情報がすぐ手に入る」など)を具体的に、そして粘り強く説明し、心理的安心安全な場での対話を通じて変化への不安を取り除き、変革への協力を引き出すプロセスが成功の鍵を握ります。
覚悟と実行力こそがDX成功の鍵
単に「Fit to Standard」という理想を掲げるだけでは、真の業務改革は実現しません。システムの標準機能との比較を通じて「Fit & Gap」分析を行い、そこで自社の非効率性を「改革の種」として発見する。そして、その種を起点に、経営の強い意志のもとで業務プロセスを再構築(Restructure)する。この一連のプロセスこそが、システム投資の効果を最大化し、企業の競争力を高める王道です。
システムの成否を分けるのは、高価な機能ではありません。問われているのは、そのシステムを、自社の業務を根本から変革するための「触媒」として使いこなす覚悟と実行力といえるでしょう。
あなたの会社では、システムは未来を切り拓くための強力な「触媒」として機能しているか、今一度見直してみてはいかがでしょうか。
「我が社は特殊」という抵抗 を打ち破り、最新システムとのGapを「業務改革の種(糧)」として活かす発見こそ、DX成功の鍵です。
この変革の知見を全社的な力に変えるには、推進者の疲弊を防ぎ、経営層から現場まで組織全体を巻き込む体制づくりが不可欠です。現場の「やらされ感」 を自発的な行動に変え、改革を業務の一部として定着させる 継続的な組織文化定着の三段階ステップを解説します。