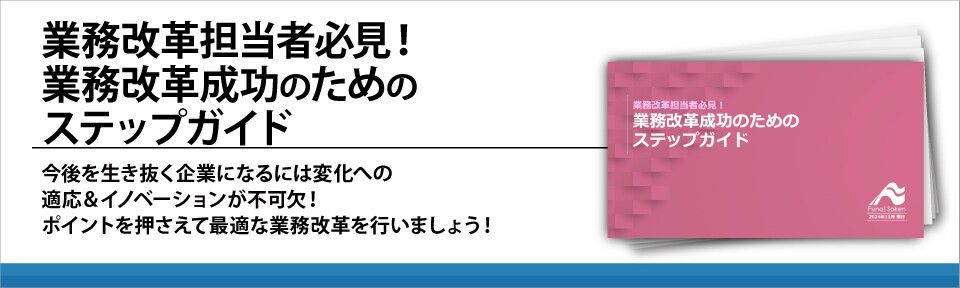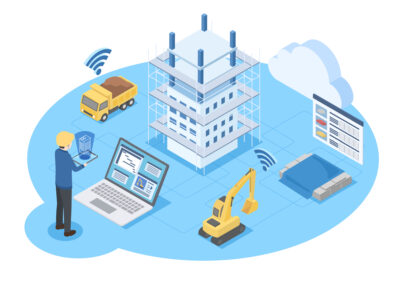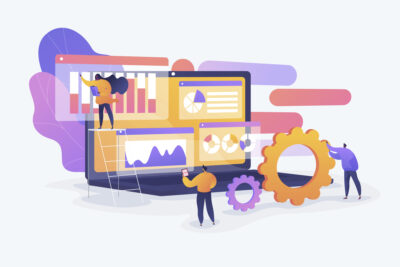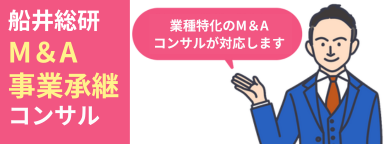そろそろ、うちの基幹システムも限界かもしれない…
長年使い続けてきたオフコンや独自開発のシステム。
画面は古めかしく、特定のベテラン社員しかメンテナンスできない「ブラックボックス」と化していないでしょうか。
毎月の締め作業では、各部署から集めたExcelファイルの数字が合わず、原因究明のために担当者が夜遅くまで残業している光景は、もはや常態化していませんでしょうか。
新しいERP(統合基幹業務システム)を導入すれば、すべてが解決するはずだ
そんな期待を抱きたくなるのは自然なことです。
しかし、それは極めて危険な兆候です。
なぜなら、あなたの会社が本当に向き合うべき課題は、古くなったシステムそのものではなく、そのシステムに紐づいた「非効率な業務プロセス」そのものだからです。
基幹システムの刷新は、単なるITプロジェクトではありません。
それは、会社の血流とも言える業務プロセス全体にメスを入れる「業務改革」という名の大手術なのです。
本稿では、製造業が抱える「あるある」な課題を紐解きながら、なぜシステム刷新に業務改革が不可欠なのか、そして、その改革をどう乗り越えればよいのかを、共に考えていきたいと思います。
あなたの会社の課題はどれですか?
製造業の心臓部ともいえるバリューチェーン。その流れのどこかに、把握しているものの改善に着手できていない課題は生じていないでしょうか。
ここでは、多くの製造業が抱える部門ごとの根深い課題を、より具体的に掘り下げていきます。
1.【設計・開発部門】「神Excel」と乱立する類似部品の呪縛
(1)BOM(部品表)が部門ごとにバラバラ問題
設計部門が使う「設計BOM(E-BOM)」、生産管理が使う「製造BOM(M-BOM)」、購買部門が使う「購買BOM」。
それぞれが独立したExcelファイルで管理され、設計変更があるたびに各部門への連絡と手作業での修正が発生。
その結果、情報の鮮度が落ち、手配ミスや製造ミスを誘発する。「最新版はどれだ?」という確認作業だけで、一日が終わってしまう…。
(2)類似部品の大量発生
ちょっとした仕様変更や顧客ごとの特別対応の結果として類似部品が大量に生まれ、在庫の増加や管理コストの増大を招いています。
過去の部品情報を探すのも一苦労で、流用設計によるコストダウンの機会も逃しています。
2.【調達・購買部門】勘と経験頼みが生む、過剰在庫と欠品のリスク
(1)KKD(勘・経験・度胸)発注の限界
需要予測の根拠が、営業からの曖昧な情報と、担当者の長年の「勘」。
その結果、必要のない部品を大量に抱える「過剰在庫」と、生産に必要な部品が足りない「欠品」が同時に発生。
結局は安全在庫を多めに持つことになり、キャッシュフローを悪化させています。
(2)発注業務の属人化
「あの部品の発注は、Aさんじゃないと分からない」。特定の担当者に業務が集中し、
その人が休んだり退職したりすると、途端に業務が滞る。サプライヤーとの価格交渉の経緯や納期調整のノウハウが個人に蓄積され、組織としての購買力強化につながっていません。
(3)サプライヤーとの非効率な連携
発注や納期確認のやり取りが、いまだに電話、FAX、メール中心。注文書(PO)の送付漏れや、
納期回答の見落としといったヒューマンエラーが後を絶たず、サプライチェーン全体のリードタイムを長期化させています。
3.【製造・生産管理部門】「絵に描いた餅」の生産計画と、見えない現場
(1)実態と乖離した生産計画
日々、営業から飛び込んでくる特急案件や急な仕様変更。それらを加味せずに立てられた月次・週次の生産計画は、初日から崩壊し、
「絵に描いた餅」と化します。現場は度重なる計画変更に振り回され、段取り替えが頻発。生産性が上がるはずもありません。
(2)現場の進捗が分からないブラックボックス
「あの製品は今、どの工程にあるのか?」それを知るためには、現場に電話するか、直接見に行くしかない。
リアルタイムに進捗を把握できないため、問題が発生しても発見が遅れ、納期遅延の根本原因になります。
実績収集も、一日の終わりに作業者が紙の帳票に手書きし、それを事務員がシステムに手入力する…といった非効率な運用が残っていませんか。
(3)品質データが活用されない
不良が発生した際、その原因を究明するために、過去の膨大な紙の検査記録を引っ張り出す。
データが蓄積されていても、分析できる形になっていないため、不良の再発防止や品質の安定化に活かせていません。
「なぜこの不良が起きたのか」を個人の経験則で判断してしまいがちです。
4.【営業・販売・経営層】見えない、分からない、決められない
(1)営業:「納期はいつ?」に即答できない
顧客から最もよく聞かれる質問に、自信を持って答えられない。生産管理部門に電話で確認し、
折り返す頃には顧客の熱は冷めているかもしれません。正確な在庫情報や生産の進捗状況が分からないため、貴重な販売機会を逃しています。
(2)アナログ対応により月次決算業務に追われる
各部門から集まってくるデータの形式はバラバラ。Excelでの集計、加工、突合作業に膨大な時間がかかり、
月次決算の締めが翌月の中旬を過ぎることも。これでは、経営状況をタイムリーに把握し、迅速な打ち手を講じることなど到底できません。
(3)原価等の収支状況の把握が困難
「本当に儲かっている製品はどれだ?」: 製品ごとの正確な原価が見えない。製造原価だけでなく、販管費なども含めた「本当の収益性」が分からなければ、どの製品に注力し、どの製品から撤退すべきかという重要な経営判断を誤る可能性があります。データに基づいた戦略的な意思決定ができないのです。
「業務改革」の絶好の機会と捉える
では、どうすればよいのか。
答えは、システム刷新を「全社最適の視点で業務プロセスを根本から見直す、千載一遇のチャンス」と捉え直すことです。
これは、IT部門だけの仕事ではありません。経営トップが強いリーダーシップを発揮し、「我々は、このプロジェクトを通じて会社をこう変えるんだ」という明確なビジョンを示すことから始まります。
そして、部門の壁を取り払い、設計、購買、製造、営業、経理といったすべての関係者が一堂に会して、「あるべき姿(To-Be)」を徹底的に議論するのです。
業務改革を伴うシステム刷新のステップ
➀現状業務の徹底的な可視化(As-Is)
まず、自社の現状を直視することから始めます。「誰が、いつ、どこで、何を、どのように行っているのか」。普段当たり前だと思っていた業務フローを一つひとつ可視化していくと、「なぜ、こんな無駄な作業を?」「この承認プロセスは本当に必要か?」といった課題が次々と浮かび上がってきます。これは、自社の健康診断のようなものです。
②「あるべき姿」の共創(To-Be)
次に、部門の利害を超えて、会社全体として理想の業務プロセスを描きます。「BOMを一元管理できれば、手配ミスがなくなり、設計変更にも迅速に対応できる」「生産実績がリアルタイムに把握できれば、営業は正確な納期回答ができ、顧客満足度が上がる」「正確な原価が見えれば、本当に儲かる製品に経営資源を集中できる」。そんな未来の姿を、全員で共有するのです。
➂新業務とシステムのフィット&ギャップ分析
描いた「あるべき姿」を、新しいシステム(ERP)の標準機能でどこまで実現できるかを確認します。そして、実現できない部分(ギャップ)を洗い出します。
➃「業務」を「取捨選択」する勇気
ここが最も重要です。ギャップが見つかった時、「システムをカスタマイズして、今の業務に合わせよう」と考えるのではなく、「システムの標準機能に合わせて、業務のやり方を変えよう」「本当に必要な業務とは何だろう」と考えるのです。なぜなら、ERPに組み込まれたベストプラクティスは多くの企業の知見が詰まった、いわば「成功の方程式」だからです。このBPR(ビジネスプロセス・リエンジニアリング)こそが、業務改革の核心です。カスタマイズしてまで守るモノは「経営トップのビジョンに則した本当に必要なプロセスとして選ばれたモノ」だけに絞りましょう。
もちろん、この道のりは平坦ではありません。
何年も掛けて築き上げ長年慣れ親しんだ仕事のやり方には、誇りもこだわりもあることでしょう。
変化に対する現場からの抵抗もあるでしょう。部門間の調整は困難を極めるかもしれません。
しかし、この「業務改革」という名の大手術を乗り越えた先にこそ、本当の果実が待っています。
■データドリブン経営の実現
部門を越えてデータがリアルタイムに連携され、経営層は正確な情報に基づいた迅速な意思決定が可能になります。
■圧倒的な生産性の向上
無駄な手作業や部門間の調整業務がなくなり、従業員はより付加価値の高い、創造的な仕事に集中できます。
■市場変化への俊敏性(アジリティ)
プライチェーン全体の情報が可視化され、顧客からの急な要求や市場の変動にも、迅速かつ柔軟に対応できる強靭な体質が手に入ります。
■持続的な成長基盤の確立
業務プロセスが標準化・最適化されることで、属人化が解消され、企業の成長を支える強固な経営基盤が築かれます。そして、導入に関わった次世代が会社の動きを理解して自立する絶好の機会です。
あなたの会社が抱える、あの「あるある」な課題。
それは、日々の業務に追われる中で、見て見ぬふりをしてきた課題かもしれません。
しかし、基幹システムの刷新というタイミングは、その根深い課題に全社一丸となって向き合う、またとない機会です。
これは、単なるコストのかかるIT投資ではありません。
会社の未来を創るための、最も重要な「戦略的投資」なのです。
「あの課題」に、本気でメスを入れてみませんか?
その先には、必ずや、より強く、よりしなやかな企業の姿が待っているはずです。
基幹システム刷新や業務改革が理想通りに進まない現実に、頭を悩ませていませんか?
本資料では、改革を成功に導くために不可欠なステップを具体的に解説。ありがちな失敗を乗り越え、着実に成果を出すための実践的なノウハウを記載していますので、ぜひご活用ください。