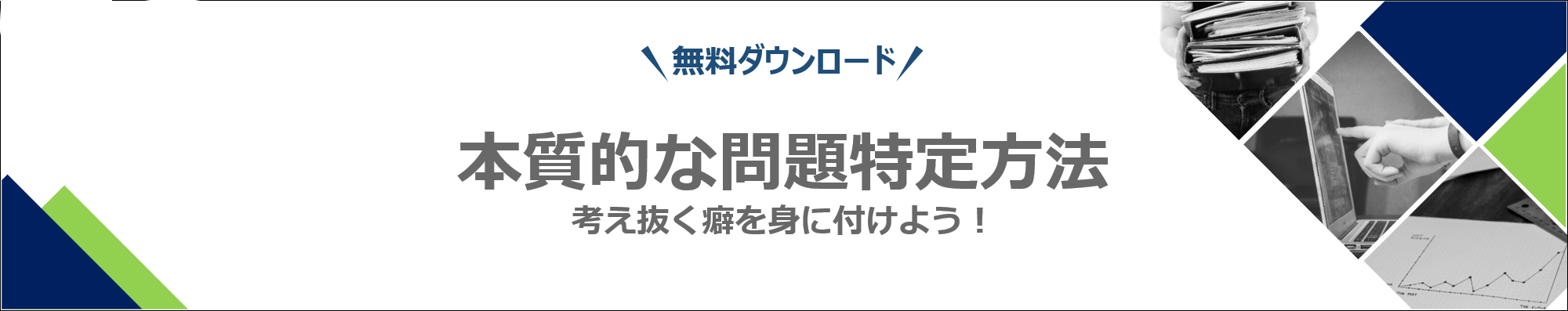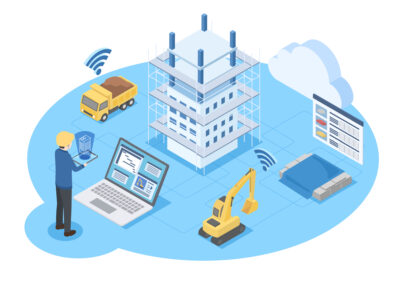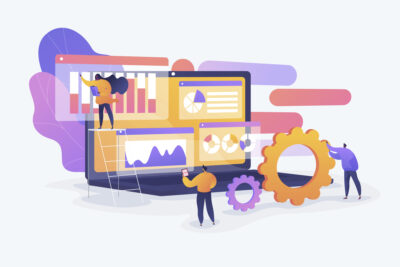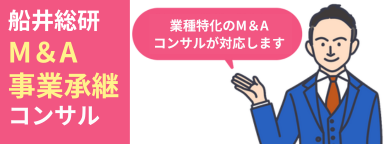業務改革の第一歩 As-Is把握
企業が成長・変革を目指す上で不可欠なのが、自社の現状を正しく理解することです。
As-Isを把握する有効な手段が業務フローの整理です。これは、業務を「誰が」「何を」「どう進めるか」をプロセスとして可視化する作業ですが、
単なる手順の羅列ではなく、関係部署や使用システム、ルールなどを網羅的に整理することで、潜在的な課題を抽出することが可能になります。
例えば、誰かにしかできない属人化された業務や、無駄な手作業、部門間の情報分断などがあげられます。
業務フローによって見えてきた課題は、定量・定性の両面から深く掘り下げます。
定量的な分析では、業務にかかる時間やコスト、処理件数といった数値データを活用し、非効率性の度合いを客観的に把握します。
一方、定性的な分析では、関係者へのヒアリングを通じて、数値には表れない課題や現場の取り組みなど、課題の本質を捉える現場の一次情報を収集します。この両面からのアプローチが、As-Isの正確な理解と、その後のDX戦略の成功に繋がります。
理想の姿を描くTo-Beの設計
現状が正確に把握できたら、To-Be設計に進みます。
To-Beとは、企業が目指すべきあるべき姿であり、将来のビジネスプロセス、組織体制、システム像を具体的に描くことです。
しかし、Tobeは単なる理想論ではありません。企業の経営戦略や事業目標、顧客のニーズに基づいた、実現可能なビジョンであることが重要です。
このTo-Be設計においては、目的と目標を明確にすることが大切です。例えば、「経理業務の効率化」という漠然とした目的ではなく、「承認プロセスの自動化によって、決算業務にかかる時間を50%削減する」といった具体的な目標を設定します。このように数値で測れる具体的目標を設けることで、プロジェクトの進捗や最終的な成果を客観的に評価できます。目的と目標が曖昧なままでは、プロジェクトの方向性が定まらず、計画が迷走する原因となります。
真の業務課題を見出す課題分析
把握したAs-Isと設計したTo-Beを比較することで、両者の間に存在するギャップが明確になり、それが真の業務課題として浮かび上がります。
課題の解決には、可視化されたAs-Isから問題事象を洗い出し、その根本的な原因(真因)を深く掘り下げることが不可欠です。
さらに、深掘りして明らかになった真因を、以下のような観点から区分けすることで、解決策の優先順位をつけやすくなり、より戦略的なアプローチが可能になります。
- 1.業務プロセス課題:業務務の進め方や手順そのものに潜む非効率性。例えば、二重入力、無駄な承認ステップ、情報共有の遅延など。
- 2.組織・人材課題 :組織構造や人員配置、スキル不足、部門間の連携不足など、人や組織に起因する問題。例えば、属人化、役割分担の不明確さ、モチベーションの低下など。
- 3.システム・技術課題 : 現状のシステムやIT環境に起因する問題。例えば、システムの老朽化、異なるシステム間のデータ連携不足、機能不足、セキュリティリスクなど。
業務課題分析はAs-IsとTo⁻Beのギャップを埋め、業務のボトルネックとなる非効率な根本原因を特定する重要なプロセスです。
この分析を通じて抽出された課題群は、今後の展開していくDXやデジタル化に向けたロードマップを策定するための基盤となります。
DXにおいて本質的な業務課題の特定がいかに重要か、ご理解いただけたかと思います。
しかし、頭ではわかっていても、いざ自社の課題を深く掘り下げようとすると、何から手をつけていいか迷ってしまうものです。
そこで、貴社の課題解決力をさらに高めるためにぜひ下記の資料もあわせてご参考ください。