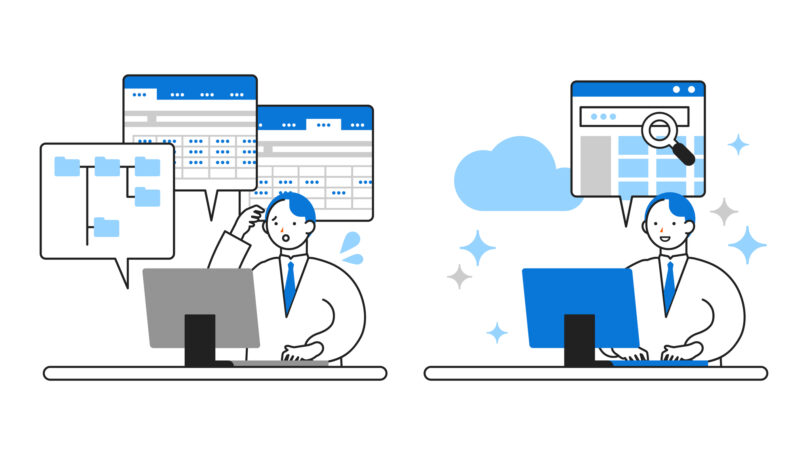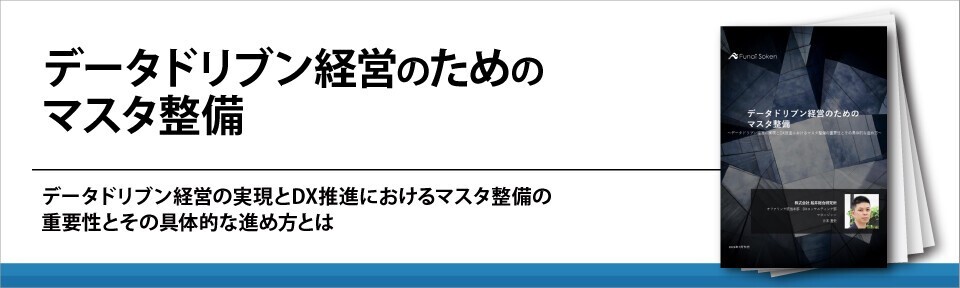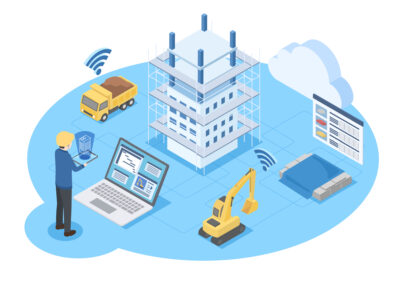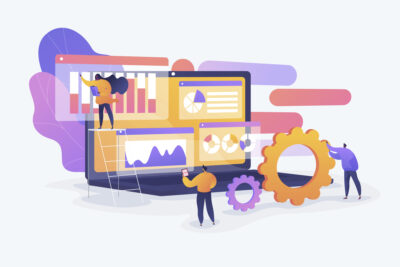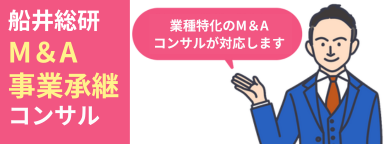なぜ今、データドリブンな経営改革が必要なのか
市場が複雑化し、AIも台頭している昨今において、勘や経験だけに頼る経営とデータ活用による意思決定を行う企業とで二極化が進んでいます。データを客観的に分析し、精度高く現状把握を行う基盤の構築が重要となります。これにより、これまで感覚的にしか捉えられていなかった課題が、具体的な数値と根拠を持った解決すべき事象として明確になります。個人の優れた経験則をデータで裏付け、組織全体の共有資産へと昇華させることが、DX時代の持続的な成長につながります。
データドリブンなDX推進の具体的なステップ
データドリブンなDX推進は、闇雲にデータを集めるのではなく、明確なステップに沿って進めることが大切になります。それは現状を正確に可視化し、あるべき姿とのギャップを明確にする、地道ですが重要なプロセスです。
まず最初に行うべきは、業務フローの整理です。これは、現在の業務が「誰によって」「どのような手順で」「どの情報(データ)を使って」行われているのかを可視化します。例えば、「受注から請求まで」の業務フローを整理すると、「営業部がお客様から受けたFAX注文書を、事務担当がExcelに手入力し、そのExcelを基に経理部が請求書を発行している」といった具体的な流れが見えてきます。この可視化された現在の姿が、いわゆるAs-Is(現状の姿)です。
次に、As-Isに対して、「なぜFAXなのだろう?」「なぜ手入力なのだろう?」といった問題点をデータに基づいて分析し、実現したい理想の業務フロー、すなわちTo-Be(あるべき姿)を描きます。例えば、「お客様がWebフォームから注文すると、そのデータが自動で受注システムと会計システムに連携され、請求書が自動発行される」といった形です。そして、このAs-IsとTo-Beを比較することで、「手入力による工数」や「転記ミスによる手戻り」といった、解決すべき課題分析が完了します。このギャップこそが、DXで取り組むべき具体的なテーマとなります。
成果に繋がるDX戦略とDXグランドデザイン
現状把握と課題分析が完了したら、いよいよDXプロジェクトの全体像を設計するフェーズへと入ります。ここで策定する「設計図」の精度が、DX投資を無駄にせず、着実に成果へと繋げるポイントとなります。このフェーズは、大きく分けて「目的地の設定」と「そこへ至るグランドデザインの策定」の二段階で構成されます。
まず「目的地の設定」にあたるのが、DX戦略の策定です。これは、DXを推進することで「どのような経営課題を解決し、どのような企業価値を創出するのか」という、企業の進むべき方向性を定めたものです。これはIT部門だけの計画ではなく、ボトムアップの意見も含めた経営戦略そのものでなければなりません。例えば、先の業務フロー改善は、「受注プロセスの効率化によって生まれた時間を、顧客へのフォローアップに充て、リピート率を20%向上させる」といった、具体的な経営目標と結びつけられて初めてDX戦略となります。この戦略の核に、データ利活用のシナリオを組み込むことが重要です。
次に「グランドデザインの策定」です。これは、DX戦略という目的地へたどり着くための、具体的な実行計画を記した全体構想図です。この設計図には、導入すべきITシステムやデータ基盤の構成だけでなく、新しい業務プロセスの詳細、そして新しいツールやプロセスを使いこなす設計書であり、自社にとっての指針になります。システムを導入して終わりではなく、組織にデータ文化を根付かせ、継続的にデータから価値を生み出し続けるための仕組みを描くことが、企業の持続的な競争力へと繋げるDXグランドデザインの役割となるのです。
本稿で解説したデータドリブン経営を絵に描いた餅で終わらせないために、不可欠なのが『マスタ整備』です。各部署でバラバラの顧客情報や商品情報を統合しなければ、どんな高度な分析も意味を成しません。データドリブン経営の第一歩、『マスタ整備』の進め方はこちらをご覧ください。